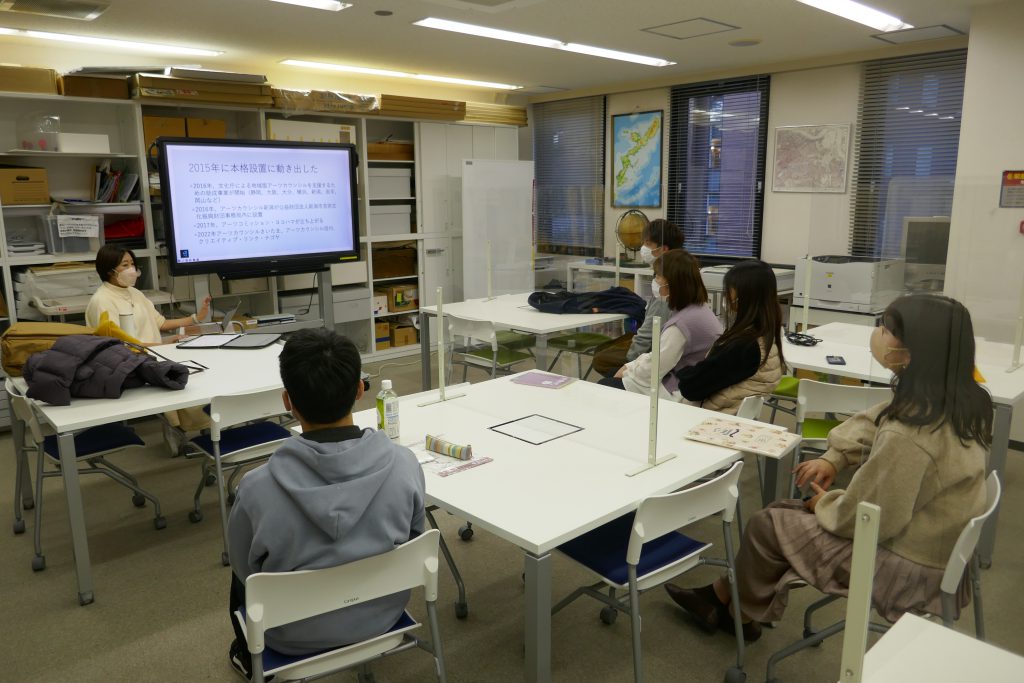| 2022年12月18日、博物館実習ⅠAの学外講義で竹中大工道具館と移住ミュージアムを訪ねました。竹中大工道具館では、鉋や木槌などの様々な大工道具や木材、昔の匠の技を学びました。今も使える「生きた道具」を展示し、音声ガイドや映像、木材や道具に触れたり、木の香りを嗅いだりと五感に強く働きかける展示が印象的でした。移住ミュージアムでは、設立の経緯や日本人のブラジル移住の歴史を説明して頂きました。国立移民収容所として実際に使っていた建物の中に当時の写真や映像、渡航時に日本から持参した道具などを展示しており、かつての情景が鮮明に伝わりました。同日に2つの異なるテーマの博物館を見学したことで、それぞれの展示法の違いや特徴が学べ、実りある時間を過せました。(2回生・福重湖雪) |